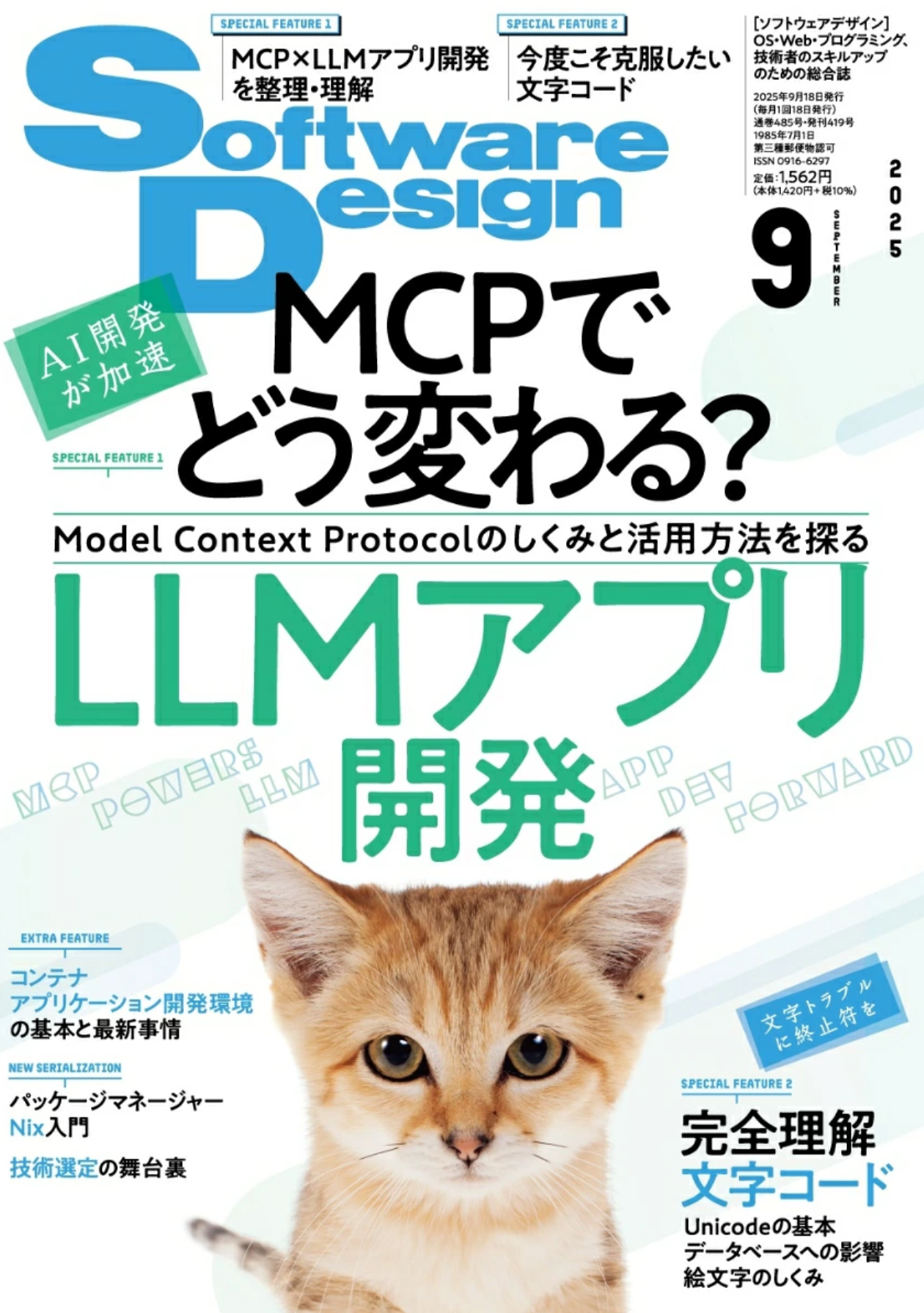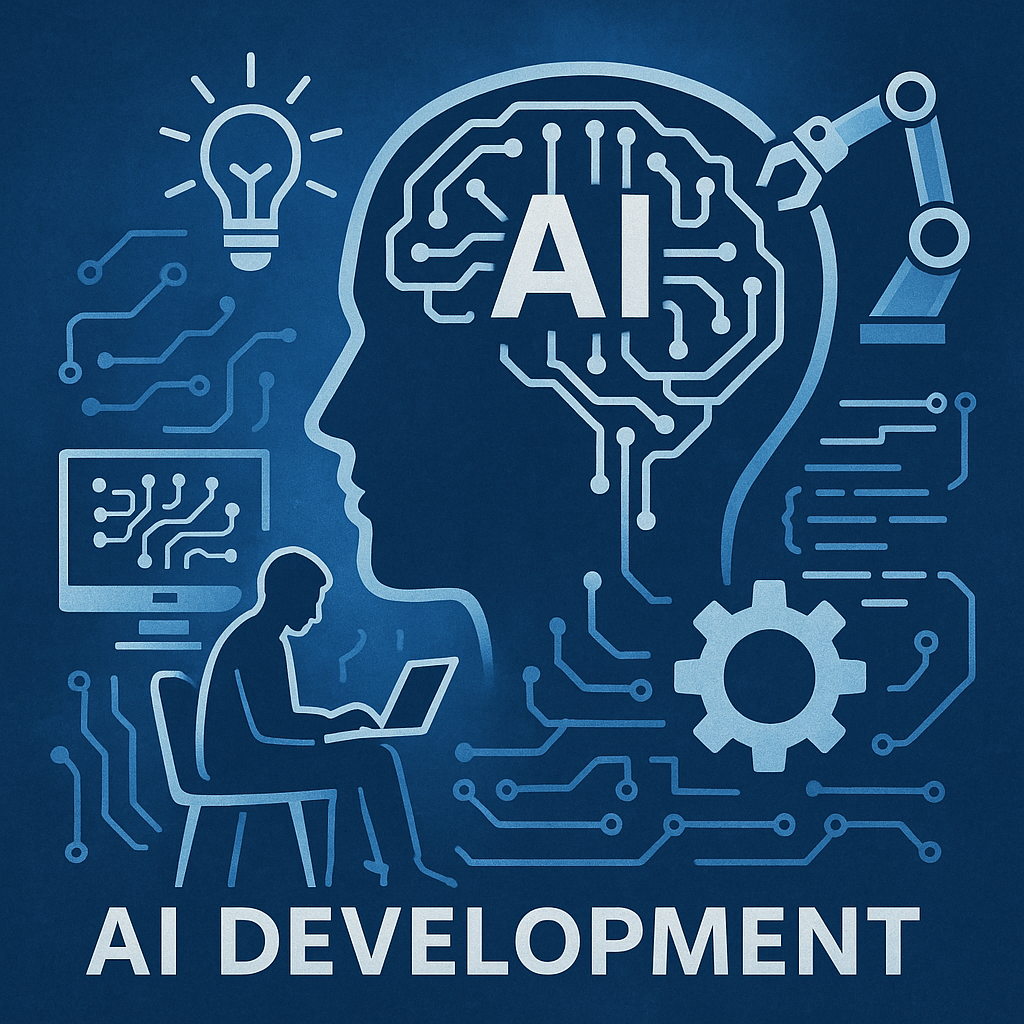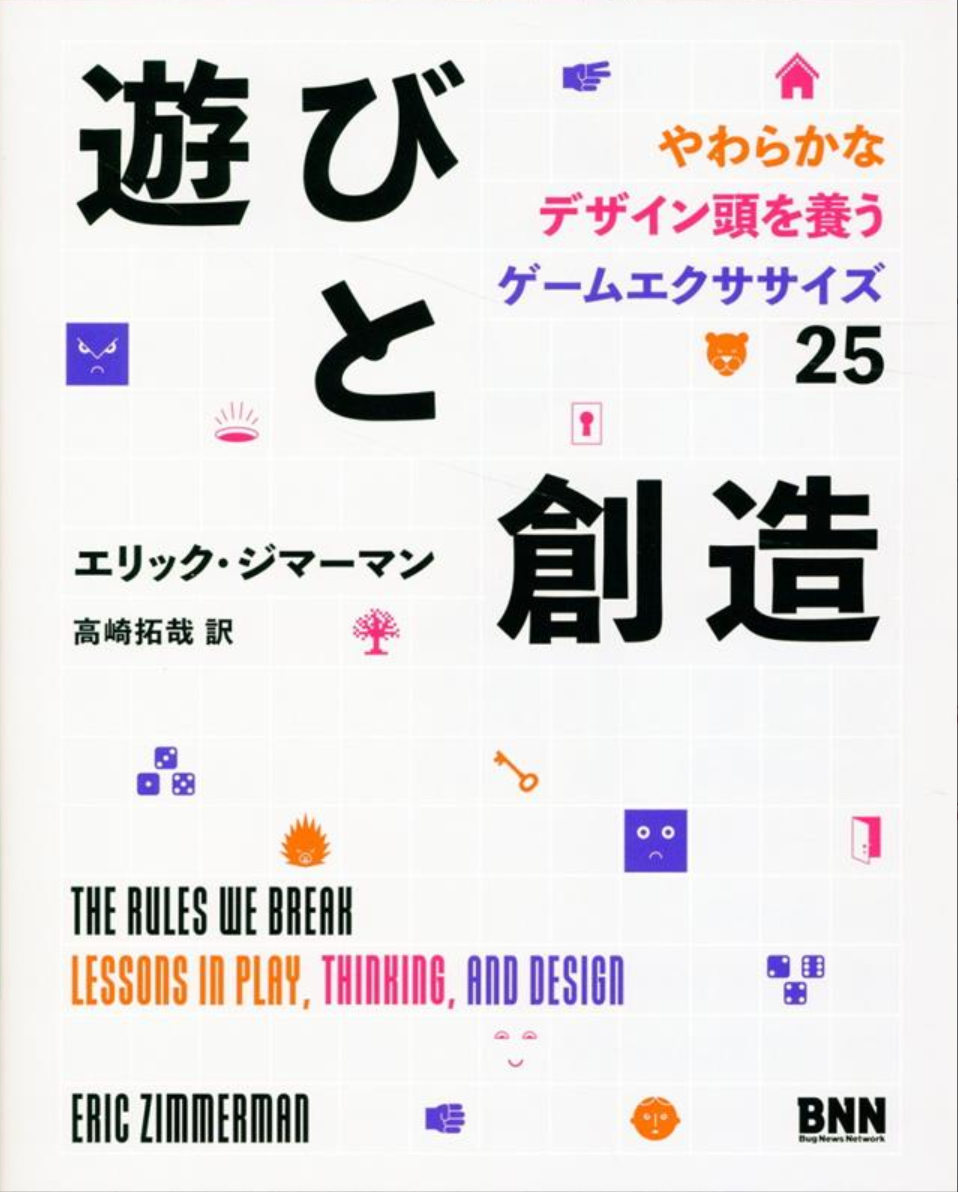AI技術がものすごいスピードで進歩している今、「どうやって外部システムとうまく連携させるか?」という課題に直面している開発者の方、多いのではないでしょうか。
Software Design 2025年9月号を読んで、その答えの一端が見えてきた気がします。今回は特に、第1特集の「MCPでどう変わる? LLMアプリ開発」について感想をお伝えしたいと思います。

MCPって何?なぜ今注目されているの?
昨年11月にAnthropicが公開し、今年3、4月にGoogleやOpenAIが採用したことで衝撃が走った「MCP(Model Context Protocol)」。正直、私も最初は「また新しい技術用語か…」と思っていました。
でも記事を読み進めていくと、これは単なる流行りの技術ではなく、AI開発における根本的な課題を解決する可能性を秘めたプロトコルだということがわかってきました。のちにMicrosoftやAWS、他のAI開発企業も追従して、今年最も注目を集める技術の1つと書かれているのも納得です。
「AI界のUSB-C」という表現が秀逸
記事の中で特に印象的だったのが、MCPを「AI界のUSB-C」と表現していた部分です。これまでAIモデルと外部システムを連携させるには、それぞれ個別にAPIを作ったり、専用の仕組みを構築したりする必要がありました。
でもMCPがあれば、標準化されたプロトコルを通じて様々なシステムと連携できるようになる。まさにUSB-Cのように、「一つの規格で全部つながる」世界が実現するかもしれません。これは開発者にとって革命的な変化ですよね。
実践的な内容が充実している
第1章から第4章までの構成も非常に良く練られていて、理論から実装まで段階的に学べるようになっています。
特に第3章の「MCPを使ったLLMアプリ開発 AIエージェントや開発環境にMCPサーバを取り込む」と第4章の「MCPを自社で活用する デザインシステムやSlackへAIエージェントを広げる」では、具体的な活用事例が紹介されており、「自分の会社でも使えそう」というイメージが湧いてきました。
文字コード特集も見逃せない
第2特集の「完全理解文字コード」も素晴らしい内容でした。文字は、あらゆる情報システムの基盤です。しかし、その裏側にある「文字コード」は、多種多様な文字表現の複雑さと歴史的経緯から、長年ITエンジニアを悩ませてきましたという問題意識から始まり、Unicodeの基礎からデータベースでの落とし穴、絵文字の仕組みまで網羅的に解説されています。
個人的には、第3章の「絵文字の符号化技術」が特に面白かったです。普段何気なく使っている絵文字の裏側にこんな複雑な仕組みがあったなんて…知らなかった世界が広がった感じです。
コンテナ開発環境の最新事情も勉強になった
特別企画の「コンテナアプリケーション開発環境の基本と最新事情」も実用的でした。LinuxでネイティブにDockerを使う場合と、WindowsやmacOSでDocker Desktopを使う場合の違いについて、パフォーマンスや使い勝手の観点から比較解説されているのが参考になります。
2025年6月にAppleから発表されたcontainer/containerizationについても触れられており、最新動向をキャッチアップできるのも嬉しいポイントでした。
連載記事も充実
メイン特集以外の連載記事も相変わらず充実していますね。特に「万能IT技術研究所」では中原中也を題材にした写真撮影の話が展開されていて、技術誌なのにこんな切り口もあるのかと感心しました。
「ネコ、コード、ネコ」シリーズも第3回を迎え、今度はエンジニアの採用について。技術的な話題だけでなく、キャリアやチームビルディングの視点からの記事も充実しているのがSoftware Designの魅力だと思います。
AI時代の開発者として考えさせられた
今回の号を読んで改めて感じたのは、AI技術の進歩が開発の世界に与えるインパクトの大きさです。AI時代の新たな波に乗り遅れないように、最新技術を押さえましょうという呼びかけは、決して大げさではないと思います。
MCPのような標準化技術が普及すれば、AIを活用したアプリケーション開発の敷居がぐっと下がるでしょう。一方で、文字コードのような基礎技術の理解も依然として重要。新しい技術を追いかけながらも、基本をおろそかにしてはいけないということを改めて認識しました。
まとめ:未来への準備ができる一冊
Software Design 2025年9月号は、AI開発の最前線を知りたい人にとって必読の内容だと感じました。MCPという新しい技術について体系的に学べるだけでなく、文字コードという基礎技術についても深く理解できる、バランスの取れた構成になっています。
特に、AIアプリケーション開発に関わっている方や、これから取り組もうと考えている方には、MCPの基本概念から実装方法まで一通り学べる貴重な資料になると思います。
技術の進歩が激しい今だからこそ、こうした質の高い情報源で継続的に学習することの大切さを実感した一冊でした。次号も楽しみです!